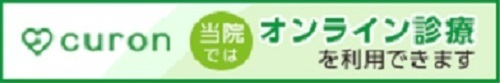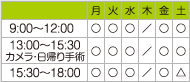苦痛の少ない胃カメラ・大腸内視鏡検査、日帰り肛門手術、やけどやキズの湿潤療法は川越駅前胃腸・肛門クリニック(埼玉県川越市)
お問い合わせいただく前にまずは
こちらをクリックしてください
音声ガイダンスでの対応となります
049-227-8686
無痛胃カメラ・大腸内視鏡検査、日帰り肛門手術、やけど・切り傷の湿潤療法は川越駅前胃腸・肛門クリニック
インフルエンザワクチン予防接種
毎年、冬から翌年の春にかけて流行し、日本での患者数は約1,000万人と推定されています。
インフルエンザワクチンの予防接種を受けておくことで、発病や入院、死亡のリスクを下げることが期待できます。ワクチンを接種することで、ウイルスを排除する働きをもった物質(抗体)を作り、次に同じウイルスが入ってきても感染しにくくなります。
接種後、約2週間で抗体ができ、免疫効果は約半年とされています。
2025年は10月1日から接種開始します。
ワクチン接種は完全予約制となります。
予約はこちらをクリック
電話での予約は行っておりません。
今年度も昨年と同様に、4価ワクチンとなります。
ワクチン接種の料金は3,500円です(2回目の接種は3,000円です)(税別)。
※当院では15歳未満のお子様へのインフルエンザワクチンの接種は行っておりません。
恐れ入りますが、かかりつけの小児科にご相談下さい。
川越市にお住いの65歳以上の方は一部助成(1500円)が受けられます。
詳細は、高齢者インフルエンザ予防接種(定期接種)をご覧ください。
3価ワクチンとは
A型インフルエンザは多くの亜型が存在しますが、B型インフルエンザには亜型がなく、2つの系統のウイルスのみが存在します。
2014年までは、流行の予測されるA型インフルエンザから2株、またB型インフルエンザウイルスより1株を選択し、合計3種類のインフルエンザウイルスに対するワクチン(3価ワクチン)を使用しておりました。通常、その年に流行するインフルエンザは、A型、B型ともに1種類ずつであったことから、B型は予測されるどちらか一方の系統しか含まれていませんでした。
一時、B型インフルエンザの2系統が同時に流行することが多くなってきたため、WHOの推奨も、従来の3価ワクチンから4価のワクチンへと変わりました。
しかし、近年、B型山形系統のウイルスは世界的に殆ど検出されなくなりました。そのため、WHO(世界保健機関)は2025/26シーズンのワクチンから山形系統を除外し、3価ワクチンとすることを推奨しました。
インフルエンザワクチン
卵アレルギーがある方に対するワクチン接種
インフルエンザワクチンは国内、国外ともに発育鶏卵内でウィルスを増殖させ、その後に精製しワクチンを製造しているため、微量の卵白アルブミンの混入を避けることはできません。
接種によるアレルギー反応で最も重篤なものがアナフィラキシーで、通常30分以内に出現し
全身の蕁麻疹・吐き気に始まり、呼吸苦や低血圧などの重篤な症状を呈します。
しかし、日本の精製度は非常に高く、ワクチン接種後のアナフィラキシーの頻度は
0.2~0.3回/100万回と推定されています。
過去に卵を食べてアナフィラキシーになった方は接種には慎重になるべきですが、症状が蕁麻疹のみであれば接種は可能です。また過去の接種で接種部位に発赤や腫脹を認めた方でも
ワクチン接種可能です。
妊娠予定または妊娠中、授乳期のワクチン接種
妊娠中は、非妊娠時に比べると免疫力が落ちて易感染状態となり、インフルエンザにかかり易くなります。さらに妊娠中は食欲不振などから体力が低下するとともに肺や心臓に負担がかかります。そのため妊婦中のインフルエンザ感染は重症化する危険性があり、積極的なワクチン接種が推奨されています。
安全性に関して米国疾病対策センター(CDC)が中心となり、調査を行っていますが、副反応の増加や胎児への影響は認められておらず、その安全性は高く評価されています。
接種時期に関しては、妊娠前、全妊娠期間で接種可能です。
また母体の抗体は胎盤を介して胎児へも移行するため、母体の免疫獲得によって出生後の乳児の感染予防と重症化防止への効果もあります。
ワクチン内の卵白アルブミンが母乳中に移行するのは極めて微量なため、お子さんに卵アレルギーがあっても授乳には問題はありません。
インフルエンザワクチンに含まれる防腐剤(チメロサール)について
チメロサールはワクチン内での細菌繁殖を予防するための保存剤として、多くの不活化ワクチンで使用されています。
ワクチン中のチメロサールについて注目されるようになったのは、ここ十数年の間に米国で
乳幼児が接種すべきワクチンの種類や本数が増え、チメロサール(エチル水銀)の投与量が
全量で375㎍にも及ぶようになったことに加えて、2000 年4月に米国でチメロサールが原因で自閉症を起こすという仮説が発表されたことに端を発しています。
しかし、チメロサールと自閉症の因果関係を示す証拠はなく、2004 年5月にIOM(Institution of Medicine ;米国科学アカデミーの医学協議会)はチメロサールと自閉症の関係を正式に否定したことにより、現時点では、チメロサールと自閉症の因果関係は否定的見解が一般的となっています。
インフルエンザウイルスの種類
インフルエンザウィルスにはA・B・Cの3型があります。毎年「流行」を起こすのはA型とB型で、中でも大流行を起こすのはA型です。
A型インフルエンザウィルスは変異が多いため、年によって流行するウイルスの型が異なります。また、A型は時々遺伝子が大きく変わるため、時折世界的な大流行(パンデミック)を引き起こします。
一方で、B型は遺伝子がかなり安定しているため、免疫が長期間続きます。
A型インフルエンザウィルスの表面にはウィルスが感染を起こす細胞に吸着するのに必要な
ヘマグルチニン(HA)と感染を起こした細胞から離れる際に必要なノイラミニダーゼ(NA)という2種類の糖タンパクが存在します。HAには16種類、NAには9種類の大きな変異が存在するため、そのかけ合わせの数だけ(16x9)A型インフルエンザウィルスが存在します。それぞれウィルスは表面の糖タンパクのタイプに基づいてH○N△と表現されます。ヒトの間で伝染する主なA型インフルエンザウィルスはH1N1、H1N2、H3N2です。
2009年までに毎年流行していたのは、Aソ連型(A/H1N1)とA香港型(A/H3N2)およびB型でした。しかし、新型インフルエンザ(A/H1N1)の世界的な感染拡大を受け、WHO(世界保健機関)は2009年6月11日に警戒レベルを最も高い「フェーズ6」に引き上げ、「パンデミック(H1N1)2009ウイルス」と命名されました。
2010年8月、この新型インフルエンザの世界的な流行状況が「ポストパンデミック(パンデミック後期)」に移行したことがWHOより宣言されました。現在は通常のインフルエンザとして取り扱われ、2011年4月1日以後、その名称は「インフルエンザ(H1N1(エイチイチエヌイチ)2009(ニセンキュウ)」とされています。
B型インフルエンザの表面にもA型と同様にヘマグルチニン(HA)ノイラミニダーゼ(NA)という2種類の糖タンパクが存在します。A型とは異なり、B型のHAやNAはそれぞれ1種類しかないため、B型インフルエンザには亜型が存在しません。しかし、HAの抗原的な違いによって、B型インフルエンザウィルスは1987年にカナダのビクトリア州で分離されたビクトリア系統と、1988年に山形県で分離された山形系統に大別されます。
C型インフルエンザにはA型やB型に存在するHAやNAは無く、その代わりにヘマグルチニン・エステラーゼ(HE)という糖タンパクが存在し、B型同様に亜型は存在しません。A型B型と異なり季節性がなく、通常は小児に罹患し一度かかると再度感染することは稀とされています。
インフルエンザの予防法
予防法としては、外出時はマスクを装着し、帰ってきたらそれを外で処分してから家の中に入るようにする、屋外から屋内に入る時にはうがいと手洗いを必ず行う、といったことが推奨されています。
インフルエンザは皮膚からは侵入することが出来ず、侵入するのは粘膜からです。粘膜に付着すると1時間以内に細胞内に侵入すると言われており、侵入する前にうがいなどによって洗い流すのが、予防として有効です。
またウィルスというのは一般的に細胞に寄生しない限り、長く生きることはできません。特にインフルエンザウィルスのようなRNAウィルスは自然界に存在するRNaseという酵素によって容易に分解されてしまうため、ドアのノブやテーブル、衣服についたものが、いつまでも感染力を持つということはありません。
つまり、ドアやエレベーターのボタンに触れたとしてもその手で自分の粘膜を触れたり、手で触れた物を食べたりしない、また家に帰ったら手洗いとうがいを徹底する、などの対策によって感染のリスクを減らすことが出来ます。