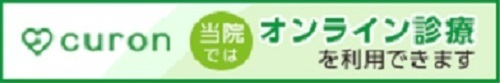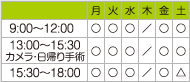苦痛の少ない胃カメラ・大腸内視鏡検査、日帰り肛門手術、やけどやキズの湿潤療法は川越駅前胃腸・肛門クリニック(埼玉県川越市)
お問い合わせいただく前にまずは
こちらをクリックしてください
音声ガイダンスでの対応となります
049-227-8686
苦痛の少ない胃カメラ・大腸内視鏡検査、日帰り肛門手術、湿潤療法は川越駅前胃腸・肛門クリニック
よくあるご質問
潰瘍性大腸炎について
Q どのような症状が現れるのですか?
A 最も多く見られるのが便の異常です。発症早期には血便以外の症状が殆どなく、痔による出血と誤り易いため、注意が必要です。
炎症が大腸の広い範囲に広がると、血便以外に下痢・軟便や腹痛などの症状を伴うことがあります。下痢がひどい場合には20回以上/日もトイレに駆け込むことがあります。さらに症状が悪化すると、体重減少や発熱などの全身症状が起こることもあります。
Q 治療で重要なことは何ですか?
A 潰瘍性大腸炎の多くは寛解(症状が落ち着いている状態)と再燃(症状が悪化している状態)を繰り返します。現状では完治させる治療法が見つかっていないため、適切な治療を維持することで再燃をコントロールし、寛解を維持することが重要です。
長期に渡り、寛解の状態を維持することができれば、外出時の度重なる便意など、日常生活に不安を抱えることなく安定した毎日を送ることが可能となります。
Q 症状が落ち着いたら薬はやめても良いのですか?
A 潰瘍性大腸炎の治療目的は、まず腹痛・下痢・血便などの症状のある「活動期」を脱し、症状のない「寛解期」へと導入することです。
寛解期になると病気でなかった時と殆ど変わらない生活を送ることができます。しかし、潰瘍性大腸炎は再燃(寛解期から再び活動期に移行すること)する可能性が高く、再燃を予防するために維持療法が必要となります。
寛解を維持し、再燃を予防するためには、薬を飲み続ける必要があります。ある2年間の調査研究では、薬をきちんと飲んでいた患者さんは約9割が緩解を維持していましたが、きちんと飲まなかった患者さんでは約6割が再燃していたとの報告があります。
Q なぜ寛解(炎症のない状態)を維持することが重要なのですか?
A 潰瘍性大腸炎の発症から10年以上経過し、病変の範囲が広い(左側大腸炎型、全大腸炎型)患者さんでは、大腸がんのリスクが高まる傾向にあります。大腸の粘膜に炎症が続くことが一因と考えられています。
薬を飲み続けることで大腸粘膜の炎症が抑えられると、合併症の予防、発がんのリスクが約半分に低下することが報告されています。
Q どのような合併症がありますか?
A 潰瘍性大腸炎の合併症には、腸管に起こるものと腸管外に起こるものがあります。朝刊合併症としては、大量出血、中毒性巨大結腸症、狭窄、穿孔、癌化などがみられます。腸管外合併症としては結節性紅斑などの皮膚症状、肝障害、関節炎など全身に起こることがあります。
中毒性巨大結腸症は炎症が急速に悪化し大腸の動きが止まってしまい、腸内にガスや毒素が溜まった結果、腸が風船のように膨らんで巨大化し、全身に中毒症状が現れることがあります。多くの場合、緊急手術を必要とします。
Q 定期的に受けなければいけない検査はありますか?
A 潰瘍性大腸炎の症状をきちんと把握するために、血液検査や大腸内視鏡検査などが行われます。
潰瘍性大腸炎の活動期には腹痛や下痢、血便といった症状が認められます。大腸の粘膜の炎症が治まってくると症状も治まってきます。
しかし、実際には自覚症状が殆どなくなっても(症状的には寛解期)、大腸内視鏡検査を行ってみると、炎症が治まり切っていないことが少なくありません。内視鏡検査で確認できる「炎症が完全に治まった状態」を「粘膜治癒」と呼び、これを達成することが重要です。
Q 「粘膜治癒」によって得られるメリットとは?
A 最近の研究結果では、粘膜治癒を達成することにより、以下の3つのメリットが得られると報告されています。
1. 再燃リスクの軽減
粘膜治癒した患者さんと、そうでない患者さんの1年間の経過をみたところ、粘膜治癒していなかった患者さんは73.9%が再燃してしまいました。一方、粘膜治癒した患者さんで再燃したのは27.5%でした。
2. 入院・手術リスクの軽減
中等症~重症であった患者さんの経過で粘膜治癒に至らなかった患者さんは、その後5年間の入院率が48.7%だったのに対し、粘膜治癒を達成できた患者さんは25.0%にとどまりました。
また、大腸切除を受けるまでに至った割合を比較すると、粘膜治癒していなかった患者さんの手術率は18.0%だったのに対し、粘膜治癒していた患者さんでは3.3%でした。
3. 大腸がんのリスクの軽減
粘膜治癒を達成した患者さんでは、粘膜治癒に至らなかった患者さんに比べて大腸がんのリスクが軽減したという報告があります。
Q 日常生活ではどのようなことに気を付けたら良いのでしょうか?
A 仕事や日常での運動を含め、病気を理由に日常生活を必要以上に制限することはありません。だからといって翌日まで疲れを持ち越すようなムリは禁物です。また過労やストレスが再燃のきっかけになることもありますので、日々の生活においては適度な安静と十分な睡眠をとり、ストレスのない生活を送るようにしましょう。趣味の時間を楽しむなどのストレスをためないよう、自分なりの対処法を身に着けておくことも大切です。
Q 食事で気を付けておくことは?
A 基本的に厳しい食事制限の必要はありません。ただし、調子の悪いときはお腹を刺激するような食事を控えるなど、セルフコントロールを心がけましょう。
活動期は腸管からの栄養の吸収が妨げられ、体力の消耗をきたすことがあるので、高エネルギー食や良質のたんぱく質、消化の良い食事が勧められています。
寛解期はそれほど神経質になる必要はありません。暴飲暴食を避けてバランスの良い食事を心がけましょう。
Q 妊娠・出産はできますか?
A 基本的に妊娠・出産は問題ありません。
ただし活動期に妊娠した場合は流産や早産などのリスクが若干高くなることから、妊娠を希望する場合は、事前に医師に相談し寛解期の状態(炎症のない状態)で計画的に妊娠されることが理想です。
最も大切なことは、初期から薬物療法を継続的に行うことにより、再燃させないようにすることです。ただし、妊娠前や妊娠中は薬物の種類や量を変更する場合があります。
Q 潰瘍性大腸炎は遺伝しますか?
A 潰瘍性大腸炎は、必ず子供に遺伝するわけではありません。
潰瘍性大腸炎とクローン病を含む「炎症性腸疾患」というくくりでみると、炎症性腸疾患の患者さんの身内に同病の人がいる確率は1~数%と報告されています。これは、そうでない人と比べれば数倍高いことになりますが、それが遺伝の影響なのか、生活環境による影響なのか、はっきりしていません。
いずれにしても、潰瘍性大腸炎の患者さんのお子さんが同じ病気になる確率は、糖尿病や高血圧などの他疾患に比べると低い確率と言えます。
Q 妊娠にあたってどのような準備が必要ですか?
A 妊娠すると、産婦人科と消化器科のどちらの診療科にもかかることになります。
消化器科では妊娠していることを伝え、なるべく寛解期に妊娠できるように病気をコントロールすることが大切です。さらに病状が悪化する場合に備え、妊娠中も潰瘍性大腸炎の診察は定期的に受ける必要があります。
産婦人科では、自分が潰瘍性大腸炎であることをきちんと説明し、母体と胎児の健康状態を注意深く観察してもらいましょう。
また、どちらの診療科にもどこの病院にかかっていいるかを伝えておきましょう。消化器科と産婦人科の両方の主治医が連絡を取り合える状態にしておくと何かあったとき、速やかに対応できます。潰瘍性大腸炎を診察できる医師がいる病院での出産が可能であれば、より安心です。